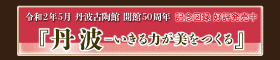古丹波 その歴史と美
平安時代の終わりに、なぜか丹波(たんば)、常滑(とこなめ)、越前(えちぜん)などに、同じ様式の壺が造られています。それらは一般的に「三筋壺(さんきんこ)」とよばれているもので、小振りでやや外に開いて立ち上がった口造りを持ち、胴の三ヵ所に横筋の文様が施されています。
須恵(すえ)の窯から、新しい窯業集落に変わったおおよそ八百数十年前、丹波の工人たちは、中央政庁や社寺のもとめに応じて祭器、経器、薬壺(やっこ)など、かなり上手物を焼きましたが、三筋壺もその一つです。しかし、陶土や窯の条件は、その目的に応えることができず、丹波窯はやがて大衆の生活を支える窯業集落として、独自の道を歩むことになります。
紐造(ひもづく)りの困難な成形、長い日時と破損の多い焼成の結果に、陶工たちはどのような思いで取り組んだのでしょうか。
今、私たちが感じる器そのもののもつ力強さや、窯業の生んだ鮮やかな緑の自然釉(しぜんゆう)も、不可抗力な焼物造りの障害の産物だったのではないでしょうか。
平安末期から慶長年間に至る穴窯(あながま)の時代は、ひたすら成形と窯とのたたかいであったのです。
慶長末年、登窯(のぼりがま)の導入によって、新しい技法を得た丹波の陶工たちは、轆轤(ろくろ)、釉薬(ゆうやく)を巧みに使い斬新な仕事ぶりをみせます。それは生活の用に即した、美しく逞しい器の数々でした。
登窯と塗土が生みだした燃えるような「赤土部(あかどべ)」の輝きは、すでに陶工の心にかけがえのない“美”として映っていたでしょう。それは、陶土の悪さに阻まれた穴窯の焼締(やきし)め無文の時代とは大きくイメージを異にするものです。
江戸時代末期になると、さらに新しい釉薬や漉土(こしつち)による陶土の改善がなされ、白、黒、灰、鉄などの釉薬の掛け合わせによる多彩な文様と、さまざまな用途をもつ器が生まれました。
平安時代末期に生まれ、いつの時代にも衰微することなく、常に生活の器を焼き続けてきた丹波焼は、間違いなく日本民陶の歴史を代表する焼物なのです。
当館の「古丹波コレクション」は、初代館長中西幸一と二代館長中西通が約80年に亘り蒐集してきたものです。